关于日本的少子化问题毕业论文
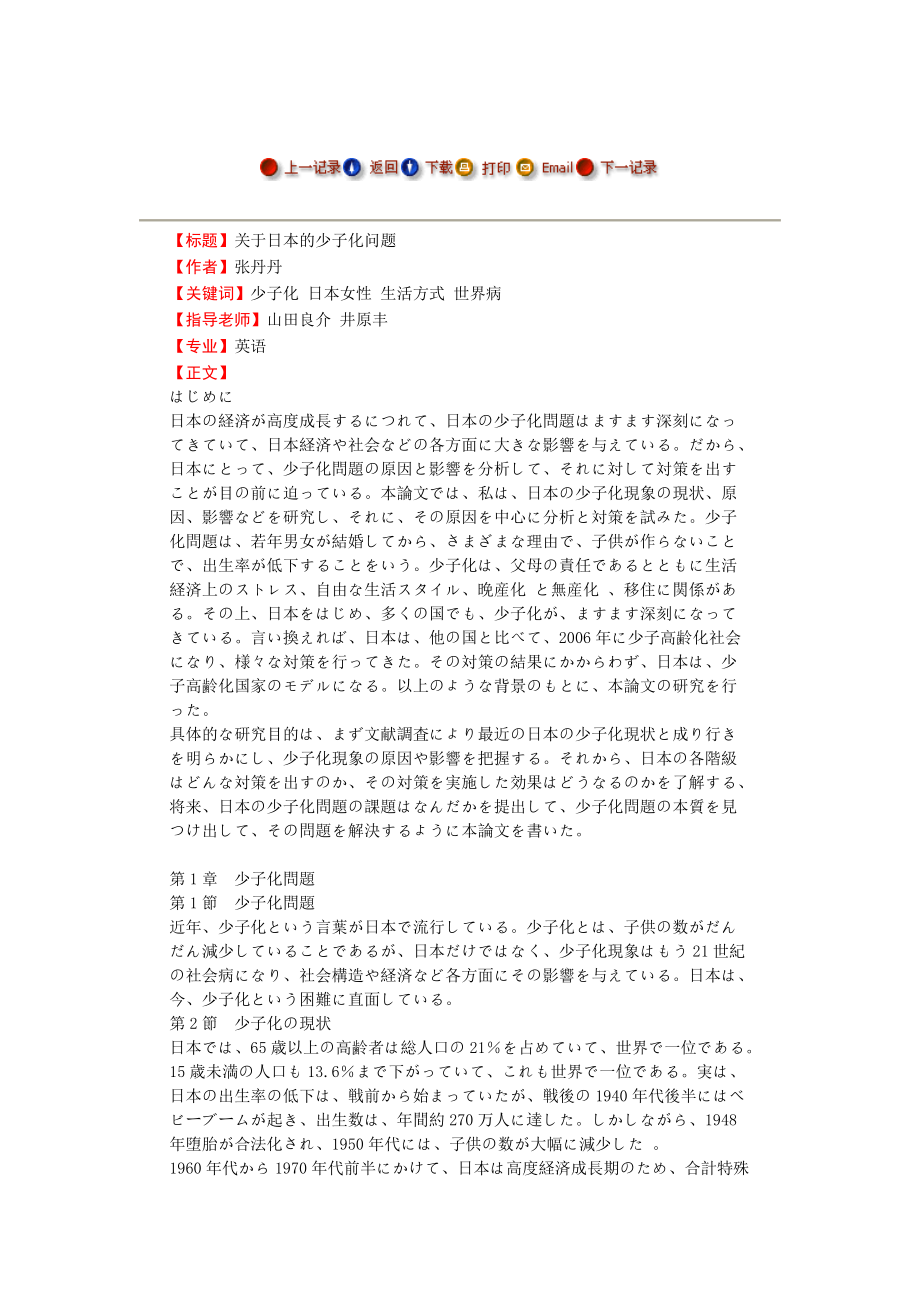
标题】关于日本的少子化问题 【作者】张丹丹 【关键词】少子化 日本女性 生活方式 世界病 【指导老师】山田良介 井原丰 【专业】英语 【正文】はじめに日本の経済が高度成長するにつれて、日本の少子化問題はますます深刻になってきていて、日本経済や社会などの各方面に大きな影響を与えているだから、日本にとって、少子化問題の原因と影響を分析して、それに対して対策を出すことが目の前に迫っている本論文では、私は、日本の少子化現象の現状、原因、影響などを研究し、それに、その原因を中心に分析と対策を試みた少子化問題は、若年男女が結婚してから、さまざまな理由で、子供が作らないことで、出生率が低下することをいう少子化は、父母の責任であるとともに生活経済上のストレス、自由な生活スタイル、晩産化 と無産化 、移住に関係があるその上、日本をはじめ、多くの国でも、少子化が、ますます深刻になってきている言い換えれば、日本は、他の国と比べて、2006年に少子高齢化社会になり、様々な対策を行ってきたその対策の結果にかからわず、日本は、少子高齢化国家のモデルになる以上のような背景のもとに、本論文の研究を行った。
具体的な研究目的は、まず文献調査により最近の日本の少子化現状と成り行きを明らかにし、少子化現象の原因や影響を把握するそれから、日本の各階級はどんな対策を出すのか、その対策を実施した効果はどうなるのかを了解する、将来、日本の少子化問題の課題はなんだかを提出して、少子化問題の本質を見つけ出して、その問題を解決するように本論文を書いた第1章 少子化問題第1節 少子化問題近年、少子化という言葉が日本で流行している少子化とは、子供の数がだんだん減少していることであるが、日本だけではなく、少子化現象はもう21世紀の社会病になり、社会構造や経済など各方面にその影響を与えている日本は、今、少子化という困難に直面している第2節 少子化の現状日本では、65歳以上の高齢者は総人口の21%を占めていて、世界で一位である15歳未満の人口も13.6%まで下がっていて、これも世界で一位である実は、日本の出生率の低下は、戦前から始まっていたが、戦後の1940年代後半にはベビーブームが起き、出生数は、年間約270万人に達したしかしながら、1948年堕胎が合法化され、1950年代には、子供の数が大幅に減少した 。
1960年代から1970年代前半にかけて、日本は高度経済成長期のため、合計特殊出生率 は2.13名で安定していたしかし、第二次ベビーブームと呼ばれた1973年をピークとして、オイルショックが始まてから、1975には出生率が2名を下回り、出生数は200万人を割り込んだそれ以降、日本は、以前の人口安定水準を回復していない 1990年代以降も出生率低下は続き、1992年の国民生活白書に少子化という言葉が初めて使われ、それからこの言葉だんだん広まった1996年から日本の人口は減少過程に入ったその後、日本は1997年に少子化社会になった(図表1-1,1-2)図表1-1出生数と合計特殊出生率の推移(図) 出所:「人口動態統計」厚生労働省図表1-2出生数と合計特殊出生率の推移(表)年次 出生率 合計特殊出生率 年次 出生率 合計特殊出生率1947 昭和22 2,678,792 4.54 1980 55 1,576,889 1.751950 25 2,337,507 3.65 1985 60 1,431,577 1.761955 30 1,730,692 2.37 1990 平成2 1,221,585 1.541960 35 1,606,041 2.00 1995 7 1,187,064 1.421965 40 1,823,697 2.14 2000 12 1,190,547 1.361970 45 1,934,239 2.13 2005 17 1,062,530 1.261975 50 1,901,440 1.91 2008 20 —— 1.37出所:「人口動態統計」厚生労働省 2005年には総人口の減少が始まった。
同時に、このまま少子化が続いたなら、2050年に一億まで減少すると予想されて 、その上、2060年になると、6400万人に減少すると見込まれている今後も、さらに、経済不況によって出生率の低下が予想されている2009年9月3日付けのホンコンの『明報』によると 、出生率の低下は、日本で国家の盛衰を決めると言われているそうだ少子化問題の現状は厳しくて、「嵐の前の静けさ」と言われている第2章 少子化の原因と影響第1節 少子化問題の原因晩産化、無産化が少子化の主な原因である儒教伝統文化の影響した日本では、結婚して、子供を産んで、世代継続するのは、いまでも伝統の観念に揺るぎないしかし、経済の発展に伴って、若い人にはこの観念が少しも残っていないそれに反して、未婚化 、晩婚化 の進展が少子化に強く影響している或いは、結婚した場合も、経済的理由や責任を負う理由で、出産を控える傾向があるまた、離婚率が高い、移住が多いことも、少子化の原因となっている まず未婚と晩婚を選ぶ男性でも女性でも、独身生活はとても自由だと考える特に、職業がある女性はそのように考える日本の高等教育の普及のおかげで、日本の女性も教育を受けるのは普遍のことになっている。
彼女たちの高学歴化は、女性に、就職の機会を多く提供すると同時に職業があると、経済的な実力もどんどん増加し、以前と違い、夫に依存しなくても生活ができるようになる結婚すると、自分の居場所が縛られる自分一人だと、仕事も続けられるし、お金も自由になるその上、男性中心の日本社会で、男性と同一労働同一賃金になりたいなら、男性よりもっと努力しなければならない結婚と子供のため、仕事を辞めて、長い間してきた仕事を諦めて、夫に依存するのは、無理だまた、女性によっては、自分が気に入らない男性と結婚するより、むしろ独身を選ぶこのような独身貴族は、収入があるので、プレッシャーがない自分が好きなことに時間とお金を使える勉強や趣味にお金を使い、非常に満足する男性の場合には、父母と別れて独立したくないと思っている人が多い一方仕事が忙しくて、見合いをする時間さえないだから、結婚の機会が少ない知らず知らずに年齢を重ねてしまう 次に、結婚した後、子供を産まないのは、経済のせいだ日本の経済は、長い間不況で、子供を育てる費用も重くなっている日本人にとって、経済の負担の中で最も重いのは住居と子供の教育費である統計によると、幼児から大学までの教育費は父母一生所得の十分の一掛るそうで、約2000万円だ 。
このような状況では二人目の子供は要らないまたは、心理的、身体的な負担が重すぎるそれから、女性の社会的地位が上がる生活の質と量が高まりつつあり、その上、ヨーロッパからの新しい解放思想と男女平等の考えが影響して女性の思想や観念、生活方式まで変える経済のグローバル化と情報の高速化で、今日本の女性は、外のことをもっと理解し、視野も広がり、日本の伝統的な生き方どおりに生きたくないただ、自分の意欲に従い、やりたいことをやり、好きな物を食べて、子供を産むツールになりたくないと思っている現在、「男性は外で働意で、女性は家庭を守る」という分業意識が日本人の中に相変わらずある「家庭より職場」という雰囲気がある総務省の2007年の労働力の調査によると、30-39歳の男性は、一週間の一番長い勤務時間が、約50時間あるまた、60時間以上の男性も20%を占める育児中の男性は長い時間仕事を続ける状態が見える周知のとおり、働き蜂のような日本の男性仕事優先観念と長すぎる勤務時間のせいで、育児と家事の時間もないもし男性は、父親の責任がちゃんと果たせないなら、子供からの楽しさも感じられないもちろん育児経験も後輩に伝えることもできない。
そこで、妻は、育児を兼ねて、家事も分担するこれも、子供を控える要因である子供を育てながら、仕事を続ける女性にとって、負担がもっと重くなる競争が激しくなるにつれて、企業は利益を上げるため、子供がいる女性は人気がないこういう企業は、育児中の女性は家事が多いので、休みも多いし、労働効率も低いし、労力も良くないと考えるそんな女性は、レベルを高めるため、やむを得ずもっと時間をかけて勉強するそして、大家族から核家族になるに伴って、祖母が赤ちゃんの世話をするのができなくなる仕事と育児の状況について、日本労働研究機関は2003年に、一回調査を行ったその調査によると、仕事と育児が両立できないという理由で仕事を辞めた女性は30%を占めた「どうして子供を産む前後に会社を辞めるのか」の質問に対して、自分から辞めた人が52%、首になった人が5.6%いる一方、仕事と育児が両立できない理由は、休みが取れないという理由が36.0%で、子供が病気で仕事に出られないのが32.8%、幼稚園と通勤時間が重なっていると答えた女性は32.8%また、幼稚園まで送る時間がない人が28.8%を占めた このような数字は、日本女性の育児と仕事が両立できない現状を反映している。
このいろいろな原因で、人々は、赤ちゃんを産むことに対して、消極的な態度になっている女性の就職率が増加しながら、少子化も激しくなる悪循環を引き起こしている また、子供がほしいけど、病気やいろいろな原因で、産むことができない人がたくさんいる統計によると 、日本では、28万人が妊娠できない不妊症にかかっているそのほかに、避妊と産児制限の技術が高いことが少子化に影響している20世紀60年代から、コンドームの使用が普及し、女性の妊娠と出産が少なくなったそれに、人工妊娠中絶が合法化されたことで、子供がほしくない人は自由に中絶を選ぶだから、避妊技術の普及も出生率低下を促す160;ここで、注意しなければならないのは、日本政府は、育児に対しての手当てが足りないことだデータによると、1999年に、日本は社会保障費が7兆5千億円に達したその中で、高齢者に対する援助費が68パーセントを占めているが、育児手当は3パーセントだけだった育児手当が少なすぎる 私の考えでは、一部の現代青年の個人主義が拡大し、責任がないリラックス生活を追求する愛国心と民族感が欠けていて、少子化問題を無視するインターネートでの少子化についての討論の中で、「人口が減少したらどうか」という疑問を出すと、私には関係ないと考える日本青年がいる。
そのほか、若い夫婦は結婚しても、子供を作らない子供のせいでのんびりできないからだこれは、新しい経済時代と現代文明の両極端か?第2節 少子化問題の影響 人口自然増加率 の下落、人口年齢構造のバランスの破壊や家庭構造の変化は、少子化の直接の影響である少子化がますます深刻化するに従って、日本の人口自然増加率がどんどん減ってきて、2005年に総人口が減少し始めた 出生率の低下につれて、日本人口の年齢構造も大きな変化を起こしているその中で、目を引くのは、低年齢人口の減少と高齢人口の増加である1996年前、0-14歳総人口に対する比率が65歳以上の人口よりずっと高いけど、この年以降、逆転したこのような趨勢は、本世紀の50年代まで続いて、60年代から再び上がると予想されているこうなると、2056年-2060年、日本の年齢が低年齢人口の比率は、10.7%に下がり、一番低い比率になり、また、2056年-2058年には、高齢人口の比率は、35.9パーセントまで上昇し、最高になるとされている 経済の面の影響としては、主に、労働人口の減少、とりわけ30歳以下の若い労働力が減少することがある。
これも、消費が縮むということを意味する労働者も消費者である労働力が減少したら、消費減少する言うまでもなく、消費市場も経済規模も縮む高齢者は、体力や記憶力も足りないので、労働効率が低いとか、労働時間が少ないとか、退職者が増えるとか、生産力上昇はいろいろな条件に制限される頭がいい若い青年が欠けると、ハイテクノロジーの開発と国際的な様々な競争で、日本企業の実力をだんだん弱める先進国から離れてしまうかもしれない高齢者の増加は、経済市場の活力を失わせるばかりでなく、財政的には、国民の負担も重くなるすなわち、国民負担率を高める国民負担率とは、一年に税金と医療保険料と老人保険料の総和が年収入にどのくらい占めるかの比率である1970年に、日本の国民負担率が24.3%2000年には37.2%、今年には、47.4%に上昇して、2025年には、60%を超えると言われている これは、日本国民の生活水準への影響が懸念されるこのほか、少子化が進むことで、老人の介護も問題になり、子供がいない家族も増加する、子供がある家庭でも、子供の人数が少ないから、子供時代になっても友達がいないし、児童の健康と成長に不利だ。
少子化問題は、日本の教育にもマイナス面を与える実は、このマイナス面が現在問題になっているこれは、主に適齢の学生が足りないから、学校がどんどん倒産することである近年、日本経済の不況で、国民の消費水準が減る反面、教育費用はいつも高い、少子化現象の進展に加えて、適齢の学生が足りない学校がたくさんある教師の需要も減少する特に、高等教育機関が普及してから、高等教育機関は、学生数に対しての競争が激しい充分の学生数を確保して、財政収入を増大させるため、公立高校はいつも、初めの計画を変更して、入学者数を増加させる公立高校は学費の値上げ、私立大学では規定の人数が募集できないため、無条件で学生を募集するしかない少子化によりショックが最も大きいのは、規模が小さい、あるいは財政規模が小さい学校ださらに問題があるのは私立大学と地方高校である文部科学省の短期大学の調査によると、短期大学の数が1996年の598所から2008年の417所に減少し、在校学生数が、47.3万から17.2万まで減った 従って、一部の大学は倒産に陥ってしまう第3章 少子化の対策 20世紀70年代から、日本は少子化の傾向が現れた日本政府や国民が気にし出した時が1990年の1.57の危機だ。
それから、日に日に減少する出生率と人口数に対して、日本政府は一連の対策を検討し始めたこれらの対策は、「少子化対策」と呼ぶ まずは、仕事と育児を両立させるため、出産し易い環境作りに取り組み、日本政府は1994年12月には、「エンゼルプラン」を打ち出したこの計画は、少子化対策としての最初の対策である雇用環境の改善、保育サービスの充実、妊婦と赤ちゃんの医療保健、住宅と生活環境の整備などの要点を含むこの計画は1995年から1999年に実施されたエンゼルプランを実施するために政府は60億円を出した1999年にはエンゼルプランは、だいぶ目標を達したその年の12月、重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画(新エンゼルプラン)も出し続けた内容は前のと大体同じで、ただ、新しい目標を出して、もっと力を入れた さらに、2003年7月には、日本政府は、「少子化社会対策基本法」を策定したこの法律に基づき、特別機関の内閣府は、内閣総理大臣が会長、閣僚全員が委員の少子化対策会儀を設立したまた、2004年6月、「少子化社会対策要綱」を制定したこの要綱は、少子化のプロセスを変えようと、視点が三つ、課題が四つ、対策を28提出した。
日本政府は日増しに厳しい少子化が社会経済の発展によくない影響を与えてきていることを認識しただから、児童が健康に成長し、国民も育児の楽しさを体験する社会を築くのは、今必要なこどだそこで、」「少子化対策要綱」の強化ため、同年の12月には、「児童と育児の支援計画」を制定したこの計画は、以前の要綱に提出した四つの課題に沿って、2005年―2009年の具体的な内容と目標を策定したもので、プロジェクトは130ある日本政府は少子化対策の理念が、健康な子供の社会を育成することにあることから、育児は楽しいという社会まで転換するこうすることによって、国民の出産意欲を高めるように、日本の少子化対策を一歩を進めた 2006年の「新少子化対策」は、全社会の意識の改革と子供の立場で政策を出すべきだと提言したそこから、日本の出生率が挙げ戻り、政府の対策も効き目を現した少子化に伴い、高齢化に対して、2007年2月に、少子化対策会議で、「児童と家庭を支援する日本」という戦略を策定した国民が結婚と育児の理想が、現実と違っていることに関心を持ち始めた、仕事と結婚出産が両立できない構造を改善するため、きっと、通勤方式を通して、仕事と生活の調和を実現する。
その上、2007年7月に、「仕事と生活の調和憲章」を出したこの数10年、確かに、日本は一連の少子化対策を出した、でも効果ははっきりと見えていないその原因は、問題の本質をつかんでないからである目下大切なのは、労働方式の改革と仕事と育児の両立や、育児方面の支援との合作である政府は、少子化問題の厳しさを直視すべきだ国民の理想が現実と違っていることを正視して、今の構造の徹底的な改革を行い、国民を励ますべきた日本政府として、少子化現象に狙いをつけて、長期的な視野に立った政策を続けるべきであるとりわけ、若い人に日本将来の重要性を明確に示すべきである経済が発展するためには、力を入れて出産を励ます必要がないまでも、出産してほしい家庭をもっと支援すべきではないだろうか?家庭政策を制定するのは、ただ消費の増加ではなくて、育児は父母としての基本の責任であることを認識すべきであるそれと同時に、父母は働いていない時には、政府からの援助を貰えるようにすべき、特に、若い女性は出産してから、仕事を続けることだ女性は消費者だけでなく、労働者だ税金にも有益である それに、国家の政策は、若者の多様化の生活スタイルに従うべきだ、。
戦後、日本の家庭では、「夫が仕事、妻が家事と育児」とされてきた、そのやり方はもう今の現実に合わないだから、夫婦が共に働き、家庭の責任を一緒に負う形式に転化する必要があるこの点だけ見れば、少子化の原因は、長い間の男女不平等の産物だとも言えるだろうこれは、歴史の残りものだ歴史を遡ると、日本政府は女性の地位を高めるため、一連の対策を作るのは、時代の流れだ本当に力を入れて対策を取らなくてはならない幸いなことに、いまの若者は思想がもう変化した男女就職の意識の統計によると、1972年、約26.2%の日本男性は、女性が結婚する前に仕事したらいいと思う人は、1995年には11.1%だけた15%が減ったその反面、出産してから仕事をつづけてもいいと思ったのは9.75から27.3%に増加した 今の女性にとって、結婚して家庭を作たら、彼女の価値も大幅に下がるそこで、育児に迷っている そのほかに、大手企業は相応な対策を採用すべきだ例えば、育児休暇を伸ばすとか、育児手当を増やすとか、子供を産んだ女性の再就職制度を設けるとかまた、雇用人数の増加を通して、労働時間を短縮するとかしてリラックスな仕事環境を作るようにする。
女性は安心して育児をし、男性にも育児の時間がある家族では、年寄は必ず妊婦の世話をする夫も、休みの時少し家事をやるこうなれば若い夫婦は、育児の面倒がないし、一家も楽しみになる また、注意しなければならないのは、今の日本政府は、団結力が足りないで、国民も、活力と民族精神が欠けているつらくでも我慢して、輝かしい経済奇跡を成し遂げようとする民族精神がないアジアの金融危機で、韓国の女性は、自分のアクセサリーもを寄付して、韓国は真っ先に金融危機から脱出した少子化問題を解決したいなら、全民族は一緒に努力するしかないおわりに少子化現象も、21世紀の世界病である調査によると、各国で15歳以下の総人口の比率は、中国は22.9%、韓国は20.8%、アメリカは21.4%、イギリスは18.9%で、フランスは19.0%、ドイツは15.7%、イタリアは14.4%で、日本には14.3%である これらの数字は、出生率の低下は多く先進国の社会病であることをはっきりと示している21世紀の若い労働力が足りないで、少子化は必ず各国の社会体制、ひいては、世界経済の発展に悪い影響を与えることだ160;将来、日本の少子化の課題は、何であるか。
今の少子化は日本の全社会の危機として、静かに進んでいる少子化を解決するためは、じっくりと検討することが必要である言うまでもない、女性は男性と同じ仕事をし、男性と同等の地位のため努力するのは、社会の進歩であるが、人間は子供を産んで、世代継続することは、人間としての責任だ少子化の終わりは、国家の滅亡だ少子化の原因から見ると、女性の地位と意識にもかかわらず、つまり、少子化は日本の社会労働経済環境を作るとき、社会環境が不完全のため生じたものであると思うなぜかというと、まず、少子化は経済の原因から始まる日本社会は、厳しい年功序列により、若者の所得が低水準にあるそれに、所得の上昇もあまり可能性がないから、未婚、晩婚になる社会の発展につれて、育児の費用が足りない今、この制度も続いている以上の問題に対して、日本社会は、両極端になるかもしれない、何か対策を出して、若者の所得と年寄りの所得の差を縮めるべきだ、また、若者に子供を産みたい環境をつくるようにすべきだそれから、人の意識の変化、とりわけ、女性の意識といえば、「男性が外、女性が内」という伝統文化のせいではないかもし、社会労働経済環境がもう成熟したら、男女の地位が平等になり、人々の意識も、社会に従うべきだ。
だから、今の日本は、高齢者の対策を支持一方で、新しい社会性を改善すべきだと思うこれも、少子化時代に解決しなければならない課題である。




